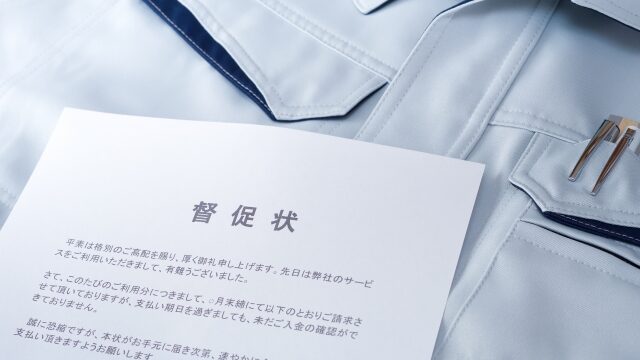近年、若い世代を中心に「将来年金はもらえなくなる」という主張が広まり、年金制度に対する不安の声があがっています。日本では急速に少子高齢化が進行しているため、現在の年金制度を維持できるのかが論点となっています。本稿では、「年金がもらえなくなる」「年金制度がなくなる」という意見の背景を述べるとともに、年金制度の持続性について考察します。
目次
- 年金制度が抱える大きな問題
- 年金制度に対する不満の声があがる原因
- 年金はなくならない
- まとめ
1.年金制度が抱える大きな問題
- 少子高齢化の進行が年金制度を圧迫する
- 厳しい年金財政
現状、年金制度は大きく分けて2つの問題を抱えています。
1つめが、少子高齢化への対応です。日本では、急速に少子高齢化が進行しており、2025年には高齢者の割合が30%と達するといわれています。このような人口構造になると、現役世代は減少し、年金受給者は増え続けることになります。
日本の年金制度は、現役世代が負担する保険料で高齢者の生活を支えるという「賦課方式」をとっています。このため、少子高齢化が進行すると、働く世代と年金を受け取る高齢者のバランスが崩れ、年金の給付水準の維持が難しくなります。
2つめが、厳しい年金財政です。日本の年金財政は、現役世代が納める保険料だけでなく、積立金の運用や税金の投入によって賄われています。積立金の不足や運用益の低下により、今後さらに財政的に厳しくなることが予想されます。
2.年金制度に対する不満の声があがる原因
年金制度に対する不満の声があがる原因を解説します。
①年金制度の複雑さ
年金制度は単純なものではなく、受給要件や支給額の計算方法などが非常に複雑です。年金制度に対する国民の理解は十分ではありません。そのため、年金制度に対する不満が増加し、将来の不安を抱える人が多くなっています。
②メディアによる煽り報道
近年、メディアが年金問題を頻繁に取り上げ、悲観的な状況を強調することがあります。年金に関する報道は、時に過剰に不安を煽ることがあり、年金に関する報道は、「年金支給額が減った」「将来はもらえない」といった内容に焦点を当てられがちです。その結果、年金制度へ不信感が広がり、将来への不安を感じることになります。メディアとしても、煽り報道をすることで注目度が高まり、視聴率やアクセス数の増加に寄与するという面があります。
3. 年金はなくならない
年金制度は、多くの問題を抱えながらも、完全に廃止となるのは現実的ではありません。その根拠となる、年金財政の仕組みを簡単に説明します。
年金財政の仕組み
日本の公的年金制度においては、少なくとも5年ごとに、財政の現況及び見通しの作成、いわゆる財政検証を実施しています。社会情勢の変化を踏まえ、年金数理に基づいた年金財政の健全性のチェックが行われています。年金財政の健康診断とイメージすると良いでしょう。おおむね100年後に年金給付1年分の積立金を持つことができるよう、年金額の伸びの調整を行っています。年金制度が安定的で、持続的なものとなるよう調整を行っているということです。
また、年金財政に関して、賃金や物価に応じて年金額を調整する仕組みがあります。これをマクロ経済スライドといい、 賃金や物価による改定率から、被保険者(現役世代)の減少と平均余命の伸びに応じて算出した「スライド調整率」を差し引くことによって、年金の給付水準を調整します。
スライド調整率=被保険者数の変動率×平均余命の伸び率
マクロ経済スライドを行うことで、現役世代と年金受給者のバランスが保たれるとともに、将来の年金の給付水準の確保につながります。
4.まとめ
現在の年金制度においては、少子高齢化と財政悪化の2つの問題を抱えています。今のままでは、年金の収支を維持することは難しいため、改革が求められています。今後の改定で、年金受給額が低下、あるいは支給開始年齢が引き上げとなる可能性はあります。この改定を、年金制度の崩壊と呼ぶ人もいるかもしれません。しかし、年金は高齢者にとって、老後の生活保障という観点で欠かせません。年金と一口にいっても、老齢年金だけでなく、障害年金や遺族年金などの年金があり、障害者や遺族にとっても重要な役割を果たしています。そのため、年金制度が完全に崩壊し、「将来年金がもらえなくなる」というのは現実的ではありません。年金制度に関する情報は、ネット上で誤解された形で広まりやすいものです。感情的な意見に流されず、正しいデータや仕組みを知ることが重要です。
<文=森 寛衆>
当ライターの前の記事はこちら:【資格紹介】NSCA-CPT とは?パーソナルトレーナーの資格を紹介
株式会社シグマライズでは、就活生向けに「就職支援コミュニティ【α】」というLINEのオープンチャットにて就活生の支援を行っています。過去のコミュニティ利用者にサポーターとしてコミュニティに残ってもらっていますので先輩に相談することも可能です。
サービスの詳細について知りたい方は、こちらのサービス紹介ページから詳細確認下さい。