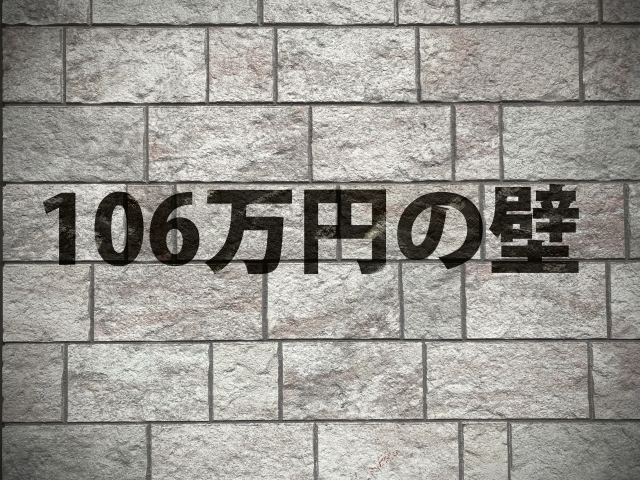「106万円の壁」という言葉を耳にする機会が増えています。
これは、パートなどの短時間労働者が社会保険に加入するかどうかの基準の1つです。
しかし現在、この「106万円の壁」は制度改正により撤廃される方向で議論が進んでいます。
一方で、「大増税なのでは?」「手取りが減って損するのでは?」といった不安の声も多く聞かれます。
本記事では、「106万円の壁」の意味、制度改正の背景、そして誤解されがちなポイントを解説します。
目次
- 106万円の壁とは?
- なぜ撤廃へ?最低賃金と制度改正の関係
- よくある誤解
- まとめ
1. 106万円の壁とは?
「106万円の壁」とは、社会保険の加入要件の一つで、賃金が月額8万8000円以上(年収換算で約106万円)のラインを指します。会社員が加入する社会保険には、扶養の仕組みがあります。一定の要件を満たせば、被扶養者として保険料の負担なく社会保険に加入することができます。
以下のすべての条件を満たす場合、短時間労働者でも社会保険の加入義務が生じます。
- 賃金が月額8.8万円(年収換算で約106万円)以上
- 従業員数51人以上の事業所であること
- 週あたりの所定労働時間が20時間以上
- 学生ではないこと(ただし、休学中や夜間学生は除く)
2. なぜ撤廃へ?最低賃金と制度改正の関係
近年、地域別最低賃金の上昇により、「週20時間以上働けば106万円を超える」地域が増えています。
例)東京都の最低賃金(1,163円)で週20時間働く
→ 1,163円 × 20時間 × 52週 =約121万円
令和6年度の最低賃金の全国の加重平均は1,055円
→ 1,055円 × 20時間 × 52週 = 約109万円
こうした実態から、地域によっては「106万円の壁」はもはや形骸化しているのが現状です。現在、この要件を撤廃する方向で閣議決定され、制度施行後3年以内に撤廃される見通しです。 最低賃金の上昇に伴い、週20時間働けばほぼ自動的に年106万円の壁を超えるため、106万円の壁の定義は不要というわけです。
3.よくある誤解
■ 誤解①:106万円の壁が撤廃されたら絶対に厚生年金に加入しなければならない
短時間労働者の社会保険加入には「収入要件」以外にも複数の条件があります(週20時間以上、従業員数要件、学生でないなど)。
つまり、月収8.8万円超えても週20時間未満の人や、50人未満の会社で働く人などは、加入対象外です。
したがって、「106万円超える=即、保険料負担が発生する(手取りの減少)」と考えるのは誤解です。
「106万の壁撤廃」により、新たに保険料負担が生じるのは、「週20時間以上働いていて、かつ年収106万未満の方」、そして他の要件を満たしている方に限定されます。
■ 誤解②社会保険に加入すると、手取りが減って損しかない
社会保険に加入すると社会保険料が徴収されるため手取りが減少しますが、その一方で得られるメリットもあります。
- 老後の年金額が増える
- 障害年金や遺族年金の保障が手厚くなる
- 怪我や病気で働けない時に、傷病手当金を受けられる
社会保険に加入することで、健康保険や年金などの社会保障が充実します。特に健康保険では、協会けんぽや健康保険組合に加入することで、傷病手当金などの給付を受けることができます。厚生年金に加入すると、老後に基礎年金に加えて厚生年金を受け取れるようになります。また、障害を負った場合には障害厚生年金、死亡した場合には遺族厚生年金を遺族が受け取れるようになります。
とはいっても、短時間労働者にとっては、現在バイアス(将来得られる利益よりも、目先の損失を強く意識してしまう心理傾向)が働くことで、手取りの減少を回避しようという意識が強くなり、労働時間を週20時間以内に抑制する労働者が増えるかもしれません。
4. まとめ
「106万円の壁」は、もともと短時間労働者が社会保険に加入するかどうかを左右する境界でした。
しかし現在は、最低賃金の上昇により、週20時間働けばこの壁を超える人が増えており、要件自体が時代に合わなくなりつつあります。 そのため、「106万円の壁」は撤廃される方向で議論が進んでいます。
また、「手取りが減るのは損だ」といった短期的な見方だけで判断するのではなく、得られる保障や年金額の増加といった長期的な視点で考えることが重要です。
<文=森 寛衆>
当ライターの前の記事はこちら:知らないと損!「加給年金」とは?仕組みと受け取り条件をわかりやすく解説
株式会社シグマライズでは、就活生向けに「就職支援コミュニティ【α】」というLINEのオープンチャットにて就活生の支援を行っています。過去のコミュニティ利用者にサポーターとしてコミュニティに残ってもらっていますので先輩に相談することも可能です。
サービスの詳細について知りたい方は、こちらのサービス紹介ページから詳細確認下さい。