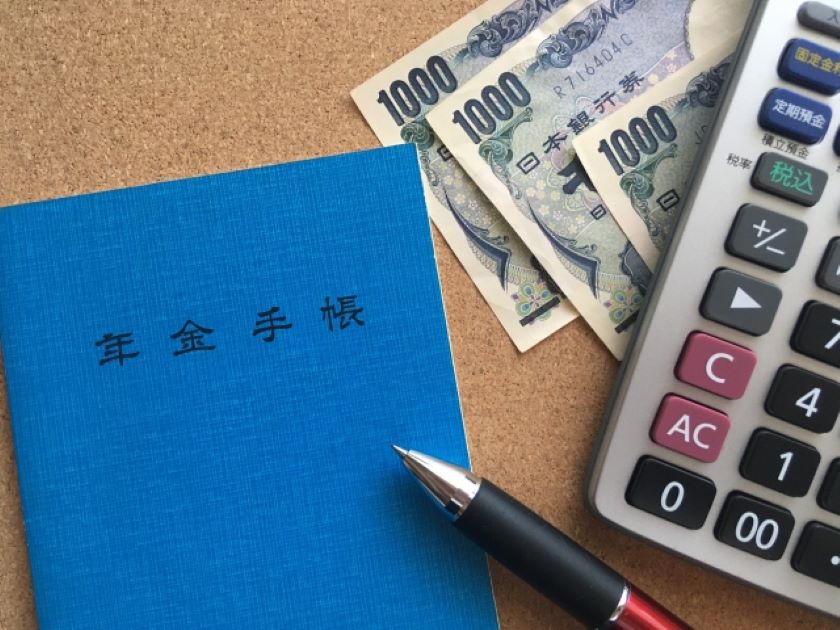今回は、国民年金の第3号被保険者廃止論について解説します。テレビやネットニュースなどで、3号廃止や年収の壁について目にした方も多いと思います。
正しく制度を理解するために、本稿では制度の概要と論点を整理します。
目次
- 第3号被保険者とは
- 背景
- 「年収の壁」が女性の「働き控え」を助長する
- 現在の対応と今後の展望
1.第3号被保険者とは
国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方を指します。第2号被保険者とは、会社員や公務員など厚生年金の加入者のことです。
現在の年金制度において、厚生年金加入者は、給料から厚生年金保険料が天引き、自営業等の方は国民年金保険料を納付しています。しかし第3号被保険者は、ご自身で保険料を負担する必要がありません。これは、第2号被保険者が全体で負担しているためです。
さらに第3号被保険者は保険料の負担なしに、老齢基礎年金を受け取ることが可能です。
第3号被保険者は、専業主婦やパートが大半を占めており、共働き世帯やひとり親世帯、第1号被保険者との間で公平性を欠くと批判されてきました。
2.背景
現在の国民年金制度発足時、サラリーマンの妻は国民年金を強制加入の対象とせず、任意で加入できる制度でした。しかし妻が任意加入していなかった場合、老後の年金だけでなく障害年金も受給できないという問題が生じました。また、離婚した場合も年金の保障がありません。
低年金・無年金問題の改善案として、昭和60年の改正でサラリーマンの妻、主に専業主婦についても国民年金の強制加入者としました。
3.「年収の壁」が女性の「働き控え」を助長する
1つめのテーマで、公平性の問題を挙げましたが、3号制度は専業主婦にとって有利な側面があります。
共働き世帯の場合、妻も厚生年金保険料を納めていますが、専業主婦は、保険料を負担していません。
制度ができた当時はサラリーマンの妻のほとんどが専業主婦でしたが、現在は働く女性が増加しています。3号制度は今の時代にそぐわないといった意見もあります。
年収130万円を超えると健康保険の扶養から外れてしまうため、扶養の範囲内で働こうする働き方があります。これがいわゆる「年収130万の壁」といわれるものです。
3.現在の対応と今後の展望
「第3号被保険者制度の廃止」はまだ決まっていませんが、制度の見直しが進んでいます。
厚生労働省は令和5年10月開始「年収の壁・支援強化パッケージ」を打ち出し、対応方針を示しました。
キーワードは「人手不足への対応」「年収の壁を意識せずに働ける環境づくり」です。
「扶養から外れないために働くことを制限する」のではなく、社会保険の加入にもメリットがあるので見直ししよう、という取り組みです。社会保険の加入には、週20時間以上の勤務や給与が月額88,000円以上等の要件があります。
政府は社会保険の加入の要件を緩和する動きを見せており、令和2年の法改正により令和6年10月から51人以上の会社で働く短時間労働者が社会保険適用の対象となりました。社会保険に加入しやすくなった結果、第3号被保険者の人数は減少し続けています。
社会保険に加入することのメリットもあります。厚生年金の加入者となると、年金を受給するときに基礎年金に加え厚生年金を受給することができます。
「3号廃止」が実現すれば、第1号被保険者となるか、厚生年金に加入することとなり、保険料を納めなくてはなりません。
第1号被保険者と同額の保険料を負担する場合、保険料は月額16,980円、年間に換算すると203,760円(令和6年度)です。
国民年金には、免除や納付猶予の制度がありますが、負担が増すのは間違いありません。
「3号廃止」は長年廃止や見直しに関する議論が行われています。
廃止が具体的には決まったわけではありませんが、社会保険の適用拡大など制度のあり方の見直しが進んでおり、現実的となってきました。ご自身で制度の仕組みを理解して、判断することが求められています。
参考
日本年金機構 https://www.nenkin.go.jp/service/yougo/tagyo/dai3hihokensha.html
厚生労働省.”年収の壁・支援強化パッケージ” https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
<文=森 寛衆>
株式会社シグマライズでは、就活生向けに「就職支援コミュニティ【α】」というLINEのオープンチャットにて就活生の支援を行っています。過去のコミュニティ利用者にサポーターとしてコミュニティに残ってもらっていますので先輩に相談することも可能です。
サービスの詳細について知りたい方は、こちらのサービス紹介ページから詳細確認下さい。