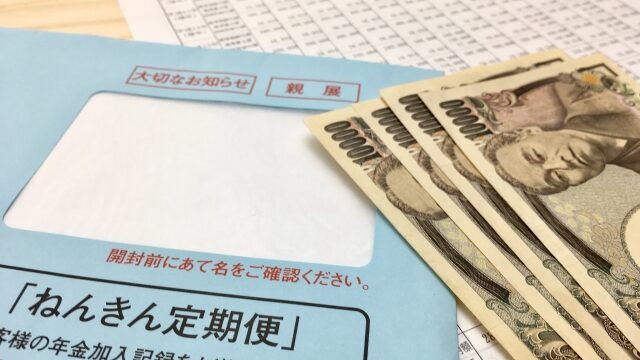目次
- 脱退一時金とは?
- 制度の盲点
- 制度の問題と将来のリスク
- 法改正と今後の課題
- 終わりに
1. 脱退一時金とは?
脱退一時金とは、外国人が日本の年金制度を脱退するときに、保険料の掛け捨て防止の目的で支給される一時金です。一般的に、外国人労働者は日本での滞在が短く、保険料を納付しても、老齢年金の受給権を獲得できない場合が多かったためです。つまり、日本に戻らない前提で創られた制度です。
対象となるのは、以下のすべてに該当する人です。(抜粋)
- 日本国籍を持たない外国人
- 厚生年金保険または国民年金の被保険者期間が6か月以上あること
- 日本に住所を有していない(=出国済)
- 年金を受ける権利を有したことがない
請求先は日本年金機構で、公的年金制度の資格喪失または出国後2年以内に申請する必要があります。
支給額は保険料納付期間に応じて計算され、上限は5年です。なお、一時金を受け取ると、それまでの年金加入期間はリセットされ、再度資格を取得しても被保険者期間に加算されません。
2. 制度の盲点
脱退一時金制度には大きな盲点がありました。日本を出国していることが支給の要件となっていますが、在留資格の喪失による出国ではなく、一時的な帰国であっても受け取れる状態になっていました。再入国許可を得たうえでの出国でも、脱退一時金が受給できていたのです。
つまり、一度社会保険の資格を喪失して脱退一時金を受給した後、再び入国して資格取得させる──このプロセスを繰り返すことで、脱退一時金受給目的の帰国という状態を作り出せてしまう構造になっていました。脱退一時金受給目的の一時帰国は、制度の趣旨を逸脱しており、明らかに不合理です。
3. 制度の問題と将来のリスク
帰国と再入国を繰り返すと、何度でも脱退一時金を請求できてしまうとともに、請求以前の全ての期間が年金加入期間ではなくなってしまいます。その結果、10年の加入が必要な老齢基礎年金の受給資格を得られずに高齢を迎える外国人が増えることになります。こうした人々が将来的に生活に困窮すれば、生活保護に頼ることになり、自治体の財政にも深刻な影響を及ぼしかねません。
脱退一時金の裁定件数は年々増加しており、直近10年間の累計は約72万件にのぼります。そのうちおよそ4分の1は、再入国許可を取得して出国していたとされており、約18万人がその後再び日本に入国した可能性があると考えられます。
4. 法改正の動きと今後の課題
近年、こうした問題を受けて、多くの自治体から国に対して制度の見直しを求める意見書が提出されました。
2025年年金制度改革法案では次のような改正が盛り込まれ、法案が参院で可決されました。
- 再入国許可を得た上での出国では、脱退一時金を支給しない
これにより、明確な制度の「抜け穴」の運用には一定の歯止めがかかります。 しかし、既に裁定され再入国した外国人労働者については改正法の効果が及びません。脱退一時金の請求に当たっては、将来日本へ再入国しない前提であるという制度の趣旨に立ち返り、さらなる実態の把握と制度の見直しを進める必要があります。
5. 終わりに
脱退一時金制度は、外国人の保険料掛け捨て防止のための制度ですが、今日まで制度の趣旨を逸脱した形で活用されていきました。これまでは脱退一時金の受給ありきで帰国と再入国を繰り返し、何度でも請求できていました。そのような外国人労働者が高齢になった際、無年金となることが予想され、結果的に地方の財政負担を圧迫する要因になります。制度の見直しによって、一定程度趣旨に沿った運用がされることが予想されますが、それでも課題が残ります。今後は制度の適正な運用だけでなく、外国人の高齢期の社会保障をどうするのかという視点からも、根本的な議論が求められます。
(参考)
名古屋市.”年金制度における外国人への脱退一時金に関する意見書”
https://www.city.nagoya.jp/shikai/cmsfiles/contents/0000183/183860/01.pdf
<文=森 寛衆>
当ライターの前の記事はこちら:年金を「損得」で考えることが間違いである理由
株式会社シグマライズでは、就活生向けに「就職支援コミュニティ【α】」というLINEのオープンチャットにて就活生の支援を行っています。過去のコミュニティ利用者にサポーターとしてコミュニティに残ってもらっていますので先輩に相談することも可能です。
サービスの詳細について知りたい方は、こちらのサービス紹介ページから詳細確認下さい。