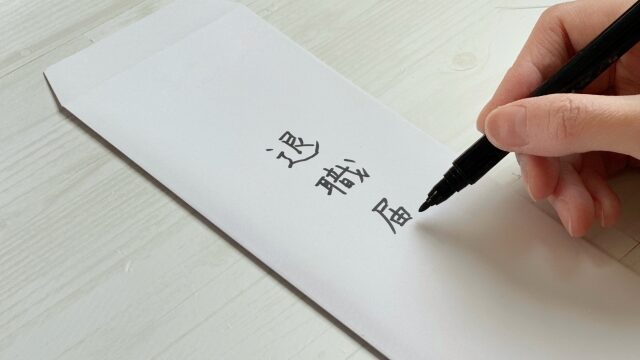「どこからがパワハラなのか分からない…」
「必要な指導をしただけなのに、パワハラと言われないか不安…」
誰しも一度はこのような疑問を感じたことがあるのではないでしょうか。今回は、パワハラについて、法律上の定義から境界線までわかりやすく解説します。
目次
- パワハラの定義
- 典型的なパワハラ6類型
- パワハラと労災認定
- まとめ
1. パワハラの定義
パワーハラスメント(以下パワハラ)は、「労働施策総合推進法」で次のように定義されています。
職場において行われる
① 優越的な関係を背景とした言動であって、
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③ 労働者の就業環境が害されるもの
この3つの要素すべてを満たすものが、パワハラに該当します。
つまり、上司・先輩など優位な立場の人が、仕事上必要な範囲を超えた叱責や暴言などを行った場合、パワハラと認められることがあります。なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、パワハラには該当しません。
2. 典型的なパワハラ6類型
厚生労働省は、典型的なパワハラを6類型に整理しています。主なものを紹介します。
①身体的な攻撃 殴る、蹴る
②精神的な攻撃 人格を否定する言動、長時間にわたる叱責
③人間関係からの切り離し
④過大な要求
⑤過小な要求
⑥個の侵害
これらの6類型は限定列挙ではなく、個別の事案について、状況を精査して判断していくことになります。実際、職場におけるパワハラに該当するか微妙なものも多く存在します。
3. パワハラと労災認定
パワハラが原因でうつ病などの精神障害を発症した場合は、労災として認定されることもあります。
労災認定の主な条件は以下の3つです。
- 精神障害を発症し、医師の診断を受けていること
- 発症前おおむね6か月以内に、業務による強い心理的負荷があること
- 業務外の要因(離婚・病気など)によるものではないこと
上司からの暴言や長期にわたる嫌がらせでうつ病を発症し、労災が認められたうえで、会社や上司に対して損害賠償(425万円)が請求された事例もあります。
4. まとめ
パワハラを適切に対応するためには、まずパワハラの定義を正しく理解することが大切です。業務上必要な指導や注意はパワハラには該当しません。そのうえでパワハラの可能性が高い場合は、社内の相談窓口や労働基準監督署に相談しましょう。
<文=森 寛衆>
当ライターの前の記事はこちら:年金制度に対する国民の不信と対策|
株式会社シグマライズでは、就活生向けに「就職支援コミュニティ【α】」というLINEのオープンチャットにて就活生の支援を行っています。過去のコミュニティ利用者にサポーターとしてコミュニティに残ってもらっていますので先輩に相談することも可能です。
サービスの詳細について知りたい方は、こちらのサービス紹介ページから詳細確認下さい。